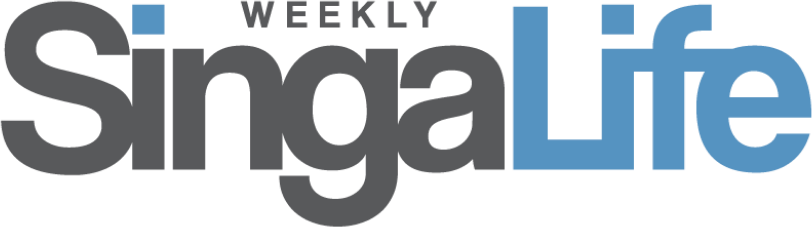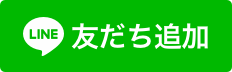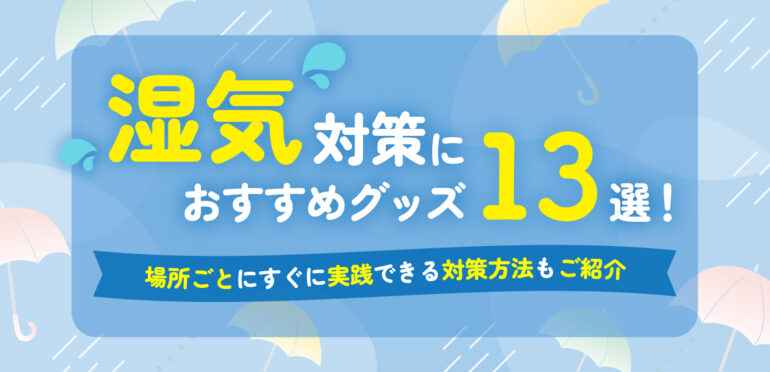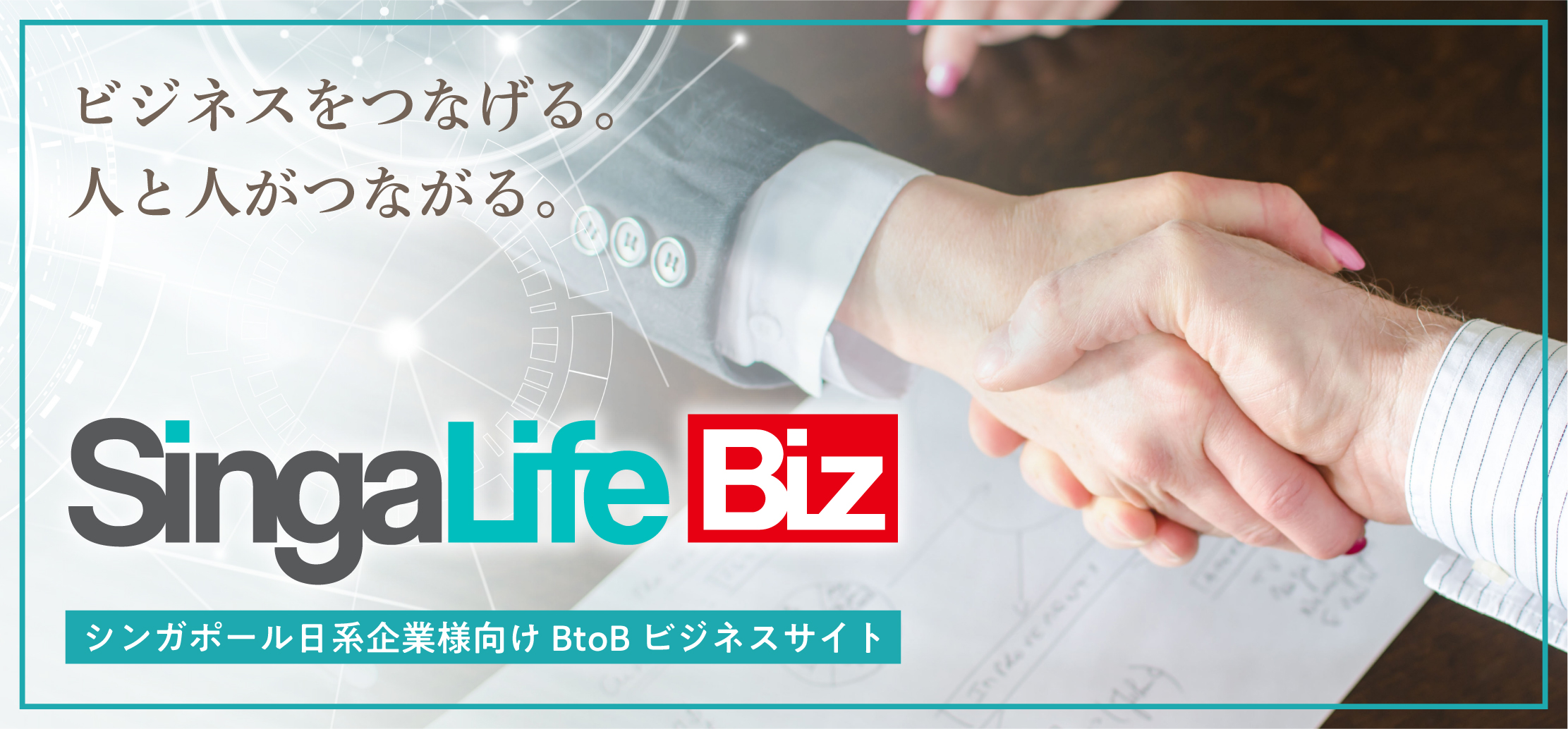【最新版】知らないと罰金!?シンガポールの厳しいルールを徹底調査 面白い罰金やルールについてもご紹介!
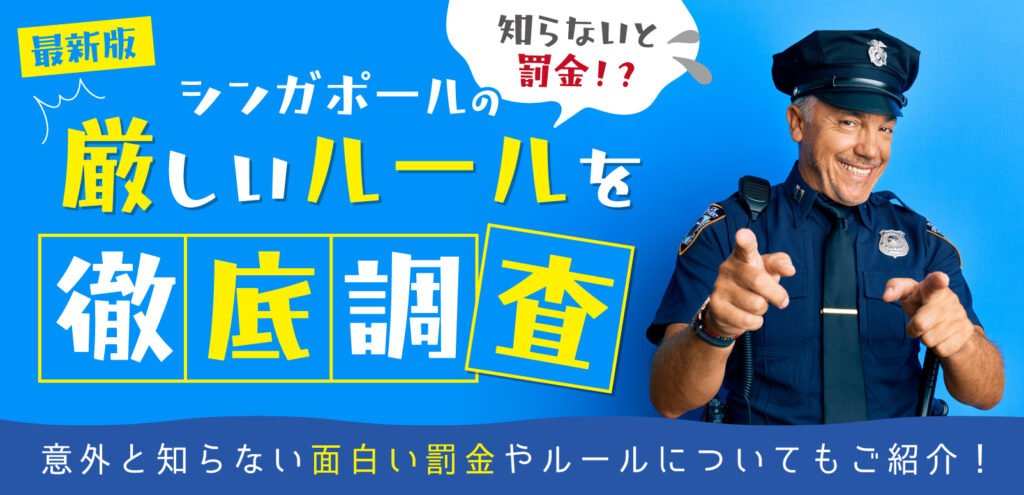
観光やビジネス、移住先としても人気の高いシンガポール。清潔で安全な国という印象のシンガポールですが、その背景には世界有数の厳しいルールがあるのをご存じですか?
シンガポールには「ガムの持ち込みで罰金」「公共の場での飲食禁止」「信号無視で懲役の可能性」など、日本では考えにくい厳しいルールが数多くあります。知らずに違反してしまうと、旅行中や生活の中で思わぬトラブルにつながることも。
今回は、2025年最新の情報をもとに、シンガポールで特に注意したい法律や罰金制度を実例とともにご紹介します。「面白いけどちょっと怖い」そんなシンガポールのルールを理解し、安心して滞在できるよう備えましょう。
シンガポールの法律が厳しい理由

シンガポールのことを「Fine City」と言う時があることを、皆さんはご存じでしょうか?
「fine」とは、”I’m fine.”(私は元気です/大丈夫です)というようなフレーズでよく使われますよね。「Fine City」と言う場合は「素晴らしい街」という意味かなと思いきや、実は「fine」には「罰金」という意味もあり、「素晴らしい街」「罰金の街」の両方の意味で使われることがあるようです。
ちなみに「fine」はラテン語の「決着をつける」という意味から派生して「罰金」という意味を持つようになったと言われています。
それでは、なぜ「罰金の街」とも言われるほど、シンガポールには、細かくて厳しいルールが多いのでしょうか?一説によれば、東京23区とほぼ同じ面積の国土に、約604万人(2024年6月現在、NTDP公式サイトより)が住んでおり、さまざまな民族と宗教からなるシンガポール国内の秩序を維持するためとも言われています。この秩序維持の背景には、厳格なルール設定があるからとも言えるでしょう。
シンガポールで生活するにあたって、どんなルールがあるのか気になりますよね。罰金を払わないようにするためにも、ぜひ知っておきましょう!
シンガポールで注意したいルール
当たり前のことから、ちょっと変わったシンガポールのルールをご紹介します!

チューインガムのシンガポール持ち込み、国内で食べることも禁止
リフレッシュしたい時や、口さみしい時には、ついチューインガムを口に入れたくなりますが、シンガポールに入国する時には、空港で検査が行われ、所持品に含まれていた場合は入国できません!また、シンガポールでは、製造も販売もされていないほか、国内で食べることも許されません。国内に持ち込んだ場合、なんと最大でS$10,000+最大1年懲役の罰金刑だそうです。
なぜチューインガムに対して、こんなにも厳しい罰則が定められているのでしょうか?
実は、1980年代の初めには、シンガポール国内でチューインガムによる問題が浮上していました。それは、チューインガムをポイ捨てすることで床などが汚れますが、取り除くために莫大な費用がかかるということでした。1992年に全面禁止され、2025年現在も没収や輸入禁止等の処置がとられています。
その後、シンガポール政府によって、国内でチューインガムの広告をしないようにメディアに働きかけるなど対策をしたものの、状況は悪化し、ついには、MRTのドアがチューインガムによって開かなくなり、交通機関に混乱をもたらす事態になり、厳しい罰則が規定されることになりました。
2004年には、禁止内容が一部緩和され、歯科治療の目的で噛むチューインガムや、禁煙治療用のチューインガムなどが認められることになりました。しかし、ほかのルールは依然として変わらないので、注意しましょう!
公共交通機関内での飲食、ドリアンの持ち込み禁止
MRTやバスなどの公共交通機関では、車内での飲食が禁止されています。外は暑いし、のどが渇いてたまらない!とつい取り出したペットボトルの水・・それももちろん罰金の対象です。またMRT構内でも飲食は禁止なので、売店や自動販売機が数多くある日本の駅に慣れてしまっていると、窮屈に感じるかもしれませんね。
ちなみに、SMT train公式サイトによると車内で飲食をしてしまった場合は、S$500の罰金となるようです。
また「フルーツの王様」と言われるドリアンは、シンガポールでも旬の季節になると、多くの人が買い求めますが、その強烈なにおいは、苦手な方にとっては耐えがたいこともあるためか、公共交通機関では持ち込みが禁止されています。また、ホテルによって禁止されているところも多いので、事前によく確認するようにしましょう!
ゴミのポイ捨て

シンガポールの小学生たちは、「ゴミをポイ捨てする人になると、黄色いベストを着せられて、みんなにゴミを捨てた人とみなされて、恥ずかしい思いをすることになるんだよ」と教えられるそうです。何気なくやってしまったかもしれない、タバコのポイ捨て、ティッシュのポイ捨て・・その代償は大きく、CWO(Corrective Work Order:是正作業命令)の実施と罰金の支払いが待ち受けています。
CWOは、公共の場で黄色いベストを着てゴミ拾いをしますが、法律違反をした人というのが一目で分かるので、なんとも恥ずかしい活動になります。さらに罰金額ですが、初犯がS$300ですが、3回目以降の有罪判決の場合はS$10,000を払うことになるそうです。
日本でもポイ捨てや不法投棄の問題など、ゴミを巡る問題は尽きませんが、一人ひとりのマナーとして身につけたいですね。
公共の場での飲酒
2015年に施行された「酒類管理法(Liquor Control Act)」によって、22:30から翌朝7:00まで、スーパーやコンビニエンスストアでのお酒の販売と、公共の場所での飲酒が禁止されました。ただし、許可を得ているレストランやバー、ナイトクラブでは22:30以降の飲酒も可能です。
また、ゲイラン地区とリトル インディア地区に設定した「Liquor Control Zones(リカー コントロール ゾーン)」では、週末や祝日、祝日の前夜は公共の場での飲酒が禁じられています。
違反した場合は、S$1,000の罰金が科せられます。日本のように、近年、年齢確認は求められるものの、コンビニエンスストアに行けば夜中でもアルコールが購入できることに比べると、とても厳しいですね。健康にはよいのかもしれませんが・・?!
シンガポールの面白い罰金刑一覧

「こんなこともダメなの?!」というシンガポールの面白い罰則をいくつかご紹介します。国が変わればルールも変わる、ということで、理解できるものもあれば、少々びっくりするものもありますが、知らないうちに罰金を払うことにならないように注意しましょう!
トイレを流さない
日本の習慣であれば、流すことは一般的だと思いますが、流さないだけで罰金に値するというのは、なかなか厳しいですよね!しかも本当にチェックするのか?!と疑いたくなりますが、検査官はしばしば巡回しているようです。
ちなみに、違反したら最高でS$1,000を超えない罰金を科せられます。こんなことで罰金は払いたくない!と思ったら、立ち去る前にダブルチェックしましょう!
公共の場でのつば吐き
公共の場でつばを吐くことは、日本でも法律で禁止されています。しかし、シンガポールでは最大S$1,000だそうです。さらに、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、唾液によって感染が拡大することが懸念されたため、取り締まりも厳しくなったようです。マナーとしても、衛生面から考えても、いいことはひとつもない行為ですね。
鳩へのエサやり
平和の象徴とも言われる「鳩」は、世界各国どの街を訪れても必ず出会う鳥ですよね。公園のベンチでひとり佇んでいると、ふと一羽の鳩がやってきたとします。「そうか、お腹が空いているんだね。」とパンくずのかけらを鳩にあげた瞬間、シンガポールでは、最大でS$10,000罰金が科せられてしまうのです!
鳩は「翼をもったネズミ」と言われるほど、病原体を拡散させてしまう恐れがある鳥ということで、シンガポールでは厳しく管理されています。自宅のベランダにパンくずを置いて、鳩のエサやり場にすることなども罰則に値するとのことで、通報もできる仕組みになっているようです。なんとも厳しい規則ですね!
また、鳩以外にも、野生動物へのエサやりは、公的な許可を得ている場合を除き、法律で禁止されており、最大でS$10,000の罰金が科せられるそうです。優しさで与えた餌があだとなるため、気を付けましょう!
蚊を発生させること
デング熱防止の観点から、シンガポールでは蚊を発生させてしまった場合、罰金が課せられます。S$5,000以下の罰金又は3か月以下の禁固刑もしくはその両方の場合もあります。
雨量も多いシンガポールですので、蚊の発生源ともなる雨水を溜めないように、日頃から注意しましょう。
公共の場での音量をわきまえない音楽
シンガポールでは、公共の場で、大音量の音楽を流すことや、他人を不快にさせるような音楽、下品と思われる歌詞を歌うことなどが禁止されています。日本でも騒音に関する規制はありますが、一方で、表現の自由に関わる問題でもあり、シンガポールよりは厳しくないかもしれませんね。シンガポールでは、違反した場合、最大S$1,000以下の罰金だそうです。
家の中で裸で歩いてはいけない
「えっ、それもダメなの?!」と思われる方が多いルール、それが「家の中で裸でいること」です!もちろん、先立つルールとして、公共の場で裸でいることが禁止されており、こちらは理解できるのですが、家の中で裸でいることを「誰が」見つけられるかというと、ご近所さんのようです。
シンガポールは高層住宅が多いこともあり、シャワー後にベランダに出てみたら、誰かの視線に裸の人が入ってしまう可能性があるということでしょうか・・?気になる場合は、部屋のカーテンを引くか、バスタオル1枚で出てくることを避けましょう!裸を見られただけで、罰金はなんと最高S$2,000以下だそうです!
横断歩道以外での横断
シンガポールでは、横断歩道や歩道橋を渡らず、車道を横切ろうとする人のことを「jaywalker」と呼んでいますが、特に、信号機や交差点、歩道橋といった地点から50m以内の場所を横切った人に対して、罰則が適用されるようです。初犯はS$50ですが、再犯はS$1,000の罰金と3か月の禁固刑、最大でもS$5,000の罰金が科せられることもあるそうです!
暑い中、信号を待ったり、歩道橋まで階段を上るのがきついと思われる方も多いのかもしれませんが、十分に気を付けたいところですね。
非常ベルを誤って鳴らしてはいけない
街中にある非常ベルを間違って鳴らしてしまうとS$5,000以下の罰金になってしまいます!非常ベル近くでボール遊びはもちろんのこと、付近を歩く際は細心の注意が必要です。
安全が十分でない、他人のネットワークを使ってしまうこと
フリーWi-Fiだと思って、見知らぬ人のネットワークに入ってしまうことはないとも限りません。しかしそれは、シンガポールではハッキングをしたことと同じとみなされ、$10,000の罰金となるようです。デジタル国家ならではの厳しいルールですね。
シンガポールの法律は他の国と比べても厳しいのか

シンガポールにはさまざまなルールがあることが分かりましたが、社会が抱える背景から生まれたものが多くあるようです。それでは、例えば日本の法律と比べるとどんな違いがあるでしょうか?いくつか調べてみました!
日本との比較
観光でもビジネスでも暮らしでも、海外に行くなら「その国ならではのルール」を知っておくことは欠かせません。とくにシンガポールのように、法律が厳格で「清潔さと秩序」が国の誇りとなっている国では、日本人にとってはごく当たり前の行動が、思わぬ形で“違法”とみなされてしまうこともあります。
ですが逆に、日本にもシンガポールの人が驚くようなルールがあるのも事実。今回はそんな日本とシンガポールの法律・ルールを比較しながら、それぞれの国の価値観に触れていきましょう。
「道路でつばを吐く」行為。日本でも軽犯罪法第1条26号により、公共の場で不快な行為(唾吐きや放尿、ポイ捨てなど)は違法とされ、拘留または科料(軽い罰金)の対象となります。ですが、シンガポールではこの行為は「衛生条例違反」として非常に重く見られており、初犯でも最大S$2,000の罰金、再犯では清掃奉仕命令(Corrective Work Order)まで科される可能性があります。
驚かされるのが、ガムの所持と販売に関するルールです。日本ではお菓子としてごく一般的に流通しているチューインガムですが、シンガポールでは原則として輸入・販売・所持が禁止されています。歯科用や処方箋に基づく医療用ガムだけが例外で、違反すると最大でS$100,000の罰金または1年の懲役刑に処される可能性があります。
これは1990年代にMRT(地下鉄)のドアがガムによって故障したことを契機に、社会全体の清潔維持を目的として導入された厳格な制度です。
公共交通内での飲食にも両国のスタンスには大きな違いがあります。日本では満員電車での飲食はマナー違反とされるものの、新幹線などでは駅弁文化が根づいており、列車内で飲食することに抵抗はありません。ところがシンガポールでは、MRTやバス内での飲食・飲水が明確に禁止されており、違反者には最大S$500の罰金が科されます。
「野生動物へのエサやり」も、シンガポールでは厳しく取り締まられています。鳩や猿、オオトカゲなどに餌を与えると、最大S$10,000の罰金が科される場合があります。日本では地域や自治体によって規制の厳しさに差がありますが、都心部では鳩への餌やりが「迷惑行為」とされ、禁止する条例も存在しています。
所持品に関する感覚の違いも興味深いところです。日本では、たとえば車にバットを積んでいたり、リュックにナイフやハサミを入れていたりするだけで、銃刀法違反とみなされる可能性があります。とくに職務質問で見つかった場合には、「正当な理由」がなければ“凶器の携帯”と見なされる恐れがあります。
一方で、シンガポールでは所持自体が違法とされることは少ないものの、公共の場での不適切な携行や使用が認められれば、「武器犯罪法」に基づき処罰される可能性があります。
シンガポールでは「騒音」にも非常に敏感です。深夜や住宅街での騒ぎ、大声、クラクションの乱用は騒音公害として違法となり、S$1,000以下の罰金が科される場合もあります。日本でも道路交通法第54条により、必要ない場面でのクラクション使用は違法とされ、5万円以下の罰金対象になります。自転車のベルも同様に、危険を知らせる目的以外での使用は認められていません。
最後に、日本独自の面白い事例を一つご紹介すると、結婚式や卒業式などの式典に乱入すると、刑法130条の「建造物侵入罪」に問われる可能性があります。これは式典を執り行っている会場を不法に侵害する行為とみなされるためで、たとえ悪ふざけであっても法的には軽犯罪法違反とされることもあります。式や儀式を重んじる日本社会らしい価値観が反映されているとも言えるでしょう。
このように、日本とシンガポールでは、同じように見える行為であっても法律や罰則、社会的な受け止め方が大きく異なることがわかります。その背景には、宗教・多民族国家としての治安維持政策や、人口密度と公共衛生を重視する都市国家としての事情などが複雑に絡んでいます。法律は国ごとの価値観を映す鏡。違いを面白がるだけでなく、その理由を知ることで、他国への理解が深まり、より豊かな旅や生活体験につながっていくはずです。
ルールを守って楽しいシンガポールライフを送ろう!
シンガポールで知っておきたいルールや法律について、2025年の最新情報をもとに代表的なものをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
どの国でも、その国の法律やルールは、ただ厳しくするために存在しているわけではなく、そこには必ず「文化的背景」や「社会的課題の解決」といった目的があるものです。シンガポールも例外ではなく、限られた国土の中に多様な民族が共生するこの国では、秩序と安全を保つためのルールが非常に重要視されています。
「チューインガムの持ち込み禁止」「MRTでの水分補給禁止」「野鳥へのエサやり禁止」といった一見ユニークなルールも、背景を知れば「なるほど」と思えるものばかり。時には、「そんなことで罰金?!」と驚いてしまうこともありますが、それこそがシンガポールらしさでもあります。
観光でも、移住でも、現地で生活するにしても、せっかくなら罰金を払うより、美味しい食事や観光、お土産にお金を使いたいですよね。そうするためにも、ぜひこうしたルールを事前に知っておき、自分自身と周りの人が気持ちよく過ごせるような行動を心がけてみてください。
ルールを守ることは、単に罰金を避けるためだけでなく、現地の文化や価値観を尊重することにもつながります。しっかりとマナーを理解して、楽しく、安心で、ちょっぴり面白いシンガポールライフを送りましょう!
●本文中の情報は、執筆時点に基づきます。
最新ニュースやプロモ情報をLINEとInstagram、メルマガでお届けしています!ぜひお友だち追加・フォローしてね!
この記事を書いた人
SingaLife編集部
シンガポール在住の日本人をはじめ、シンガポールに興味がある日本在住の方々に向けて、シンガポールのニュースやビジネス情報をはじめとする現地の最新情報をお届けします!